2024年6月10日、日本の出入国管理制度に大きな変化が訪れました。 改正出入国管理法(以下、改正入管法)の施行により、外国人の強制送還に関するルールが見直され、特に難民申請者に対する対応が厳格化されました。 本記事では、改正入管法の主な変更点とその背景、そして人道的観点からの課題について詳しく解説します。
改正入管法の主な変更点
難民申請の回数制限と強制送還
従来、難民申請中の外国人は強制送還が停止される規定がありました。 しかし、改正入管法では、難民申請は原則2回までとされ、3回目以降の申請者は「相当の理由」を示す資料を提出しない限り、強制送還の対象となります 。 この変更は、難民申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースへの対応として導入されました。
監理措置制度の導入
これまで、在留資格がなく強制送還の対象となっている外国人は、原則として収容施設に収容されていました。 改正法では、支援者など「監理人」による監督のもとであれば、送還されるまでの間、収容施設の外でも生活できる「監理措置」制度が新たに導入されました 。 また、収容中の外国人についても、3か月ごとに収容の必要性が見直されることになります。
改正の背景と目的
政府は、強制退去処分が決まったにもかかわらず送還を拒む外国人が増加し、2022年末にはその数が4,233人に達したと説明しています 。 一部の外国人が難民申請を繰り返すことで送還を回避し、収容や審査が長期化する問題が指摘されていました。 改正入管法は、こうした状況を改善し、本来保護すべき人々の迅速な救済を図ることを目的としています。
人道的観点からの課題と懸念
改正入管法に対しては、外国人支援団体などから「難民認定申請者が迫害の待つ国に強制送還されるおそれがある」といった批判が根強くあります 。 日本は難民条約に加盟しており、迫害の恐れがある国へ送還してはならないとされています。 しかし、日本の難民認定率は欧米諸国に比べて極めて低く、「難民鎖国」との批判もあります 。
また、「監理人」には違反した場合の罰則もあることから、「監理人」のなり手が集まらない事態も想定されると指摘されています 。 さらに、難民認定の審査の透明性や公平性の確保が課題とされており、政府から独立した第三者機関が審査を担うべきだとの指摘もあります 。
今後の展望と必要な対応
改正入管法の施行により、外国人の強制送還に関する制度は大きく変わりました。 しかし、人道的観点からの課題や懸念も多く残されています。 今後は、難民認定の審査の透明性と公平性を確保し、真に保護を必要とする人々が適切に救済される体制の整備が求められます。 また、「監理措置」制度の運用においても、監理人の確保や支援体制の強化が必要です。
政府は、施行後の状況を注視し、必要に応じて制度の見直しを行う姿勢を示しています。 今後の動向に注目し、外国人の人権と安全を守るための取り組みが進むことが期待されます。

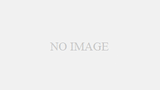
コメント