近年、「主婦年金」として知られる第3号被保険者制度の公平性や存続について、活発な議論が交わされています。
この制度は、専業主婦(主夫)の年金問題を解決するために1986年に導入されましたが、現代社会の変化に伴い、その在り方が問われています。
本記事では、主婦年金の概要、不公平性の議論、そして廃止の可能性について、詳しく解説します。
主婦年金とは?
主婦年金は、国民年金の第3号被保険者制度のことを指します。
この制度は、第2号被保険者(会社員や公務員など)に扶養されている配偶者を対象としています。
具体的には、以下の条件を満たす人が対象となります:20歳以上60歳未満である第2号被保険者に扶養されている配偶者である年収が130万円未満(2024年4月時点)かつ配偶者の年収の2分の1未満である。
第3号被保険者は、保険料の自己負担なしで国民年金(基礎年金)を受け取ることができます。
主婦年金は不公平なのか?
主婦年金制度には不公平性があるという指摘があります。
以下の点が主な批判の対象となっています:自営業者の配偶者には適用されない働いている女性との保険料負担の差が生じる現代の多様な生活形態に合わなくなっている。
パートで働く人と専業主婦の間で年金負担に差が出ることが具体例として挙げられます。
しかし、事情があって働けない人の救済措置としての側面もあり、完全な廃止には慎重な意見もあります。
主婦年金は廃止?
主婦年金(第3号被保険者制度)の廃止が検討されています。
労働人口不足や社会保障費の増加による問題が背景にあります。
連合(日本労働組合総連合会)は、この制度の廃止を求める方針を決定しました。
早ければ2025年にも廃止が決まる可能性があります。
まとめ
主婦年金(第3号被保険者制度)は、専業主婦(主夫)の年金問題を解決するために導入されましたが、現代社会の変化に伴い、その公平性や存続が問われています。
不公平性の指摘がある一方で、働けない人への救済措置としての役割も果たしてきました。
現在、廃止の検討が進められており、早ければ2025年にも決定される可能性があります。
この問題は、女性の就労や家族のあり方にも大きな影響を与える可能性があるため、今後の動向に注目が集まっています。

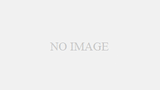
コメント